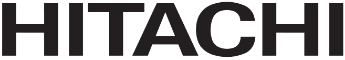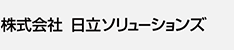人事戦略
キャリア自律支援の事例を紹介 実施の効果と注意点を解説

「人事総合ソリューション リシテア」より人事関連のお役立ち情報のご紹介です。
キャリア自律とは、個人が主体的に自分自身のキャリアを考えることです。キャリア自律という考え方は、労働人口の減少や働き方の多様化など、さまざまな要因から昨今注目を集めています。
本記事では、企業がキャリア自律を支援するメリットや注意点を解説します。キャリア自律支援の事例もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
キャリア自律とは
キャリア自律は、少子高齢化社会のなかで人材を確保していくなかで、必要性が高まっている考え方です。まずはキャリア自律の概要を解説します。
個人が主体的にキャリアを考えること
キャリア自律とは、自らが主体的にキャリアを考えて、自らの意思で継続的に学習し、自律的にキャリア開発を行うことを指します。従来の人事や上司に任せた受け身傾向のキャリア開発とは異なり、能動的にキャリア形成をめざすことが特徴です。
1990年代にアメリカで提唱された
キャリア自律は、1980年から1990年代に提唱され始めた概念であり、その起源はアメリカです。経営不況によるリストラの増加という世情の影響を受け、雇用の流動化に対応するために生まれた考え方です。近年では、キャリアオーナーシップとも呼ばれています。
自律と自立の違い
キャリア自律という表記を見て「自立」とはどう違うのかと思う人もいるでしょう。「自律」と「自立」の違いは以下のとおりです。
自律の意味
「自律」は、内面的要素における独り立ちを意味する言葉です。意志決定は自らで行い、そのうえで他者との協調や協力を必要とします。他者のニーズを把握して適切に対応しながら、自己実現をめざすのが「自律」です。
自立の意味
「自立」は、外的要素における独り立ちを意味します。自立における行動には、他者が介入しないことが特徴です。たとえば、自分の意見や主張を持っていたり、業務を自分でこなす能力を持っていたりする状態は、自立に分類されます。
キャリア自律が注目される背景
ここでは、近年になってキャリア自律が注目されている背景を解説します。
働き方が多様化した
近年はリモートワークが一般的になったほか、働き方改革によってフレックスタイム制や時短勤務も増えるなど、働き方が多様化しています。多様化した働き方のなかで着実に成果を出すためには、自分自身をマネジメントできるスキルが必要です。そこで注目されているのがキャリア自律です。
ジョブ型雇用が普及した
労働力人口の減少やグローバル化などもあり、ジョブ型雇用を取り入れる企業が増えているなかで、キャリア形成の一環としてもキャリア自律が注目されています。
ジョブ型雇用は採用形態の1つで、事業が必要としている職務や能力を定義し、適切なスキルを持つ人材を雇用する方法です。このようなジョブ型採用では、スキルや専門性が重視されるため、求職者側も戦略的にキャリアを形成する重要性が高まったといえるでしょう。
既存の雇用制度の崩壊
従来、日本の企業は一般的に、終身雇用制度や年功序列制度を取ってきました。しかし、雇用の流動化や転職のハードル低下などが原因で、既存の雇用制度は崩壊しつつあります。労働者側は、同じ企業に長く勤めるだけではポストを得られなくなりました。結果として自らのキャリアについて考えること、つまりキャリア自律が求められています。
職業能力開発促進法が改正された
職業能力開発促進法の改正は、キャリア自律が推奨される法的根拠であるといえます。職業能力開発促進法とは、労働者の能力を高め、職業の安定や地位向上を図ることを目的とした法律です。2016年や2019年度に改正され、キャリアアップや職業能力の開発が重視されるようになりました。
企業がキャリア自律を支援するメリット
キャリア自律の促進は企業側にも大きなメリットがあります。企業としてキャリア自律を支援するメリットを解説します。
エンゲージメントが向上する
企業がキャリア自律を支援することで、従業員エンゲージメントの向上が期待できます。企業のサポートを受けてキャリア自律に取り組むと、キャリアプランが明確になりやすい点がメリットです。また、従業員がサポートを実感できるため、企業に貢献しようとする意欲の高まりも期待できます。
生産性が向上する
キャリア自律によって、従業員が自身の能力を最大限発揮できるようになるため、組織全体の生産性向上が期待できます。キャリア自律は、従業員が自分自身を客観視し、自身の特徴を把握するプロセスです。特徴がわかれば長所を生かして効率的に成果を出しやすくなるでしょう。
従業員のスキルや労働意欲が向上する
従業員が自分のキャリアを考えて動けるようになると、スキルや働く意欲が高まり、効率的な人材育成ができます。キャリア自律を支援することで優秀な人材が増えやすいため、企業の成長にもつながるでしょう。
企業がキャリア自律を支援する際の注意点
企業がキャリア自律支援を行う際は、以下のような点に注意する必要があります。
転職を後押しする可能性がある
キャリア自律を促すと、多くの従業員は外部との交流が増加して視野が広くなるため、より条件のよい企業に出会うケースもあります。結果として、従業員の転職を後押ししてしまう可能性があるでしょう。キャリア自律は個人がベースとなる性質のため、転職せずに社内でキャリアを実現できるように対策する必要があります。
キャリア自律への温度感は従業員ごとに異なる
従業員のなかには、出世に興味がなく一定の収入があれば満足というタイプもいます。すべての従業員が自律を望んでいるわけではなく、現状を変えたくない人材がいる点は押さえておく必要があるでしょう。
しかし、キャリア自律は一部の従業員だけではなく、組織全体で取り組むことで高い効果を発揮します。従業員に寄り添って課題に向き合い、個々の役割を明確化しながら支援することが大切です。
企業がキャリア自律を支援するための施策
企業がキャリア自律を支援するためには、次のような施策があります。自社で実施できるものを取り入れてみてください。
キャリア研修の実施
キャリア自律を支援するためには、キャリアについて考える機会を提供する必要があります。その方法の1つがキャリア研修です。キャリア研修の実施によって従業員が自身のスキルや特性について把握でき、キャリアの明確化につながります。
キャリアに関する1on1ミーティングの実施
キャリア自律を促す有効な手段として、1on1ミーティングによるキャリアコンサルティングの実施が挙げられます。1on1ミーティングでは、ほかの従業員に気兼ねなく上司とキャリアプランについて話ができるため、自分のキャリアプランを深く考えられるでしょう。
相談窓口の設置
キャリアについて悩んでいたとしても、いつも上司に相談できるとは限りません。そこで、従業員向けにキャリアに関する相談窓口を設置すると効果的です。相談できないために退職を考えるようなケースの抑止にもなります。
キャリア意思の表明機会の用意
目的意識を持つとスキルや経験を身につけやすくなるため、キャリア意思の表明機会を用意することが効果的です。キャリアカウンセリング、上司とのミーティングなどで意思表明を促すと、従業員が自らのキャリアに意識を向けやすくなり、キャリア自律につながります。
人事制度による機会提供
社内公募制度や社内FA制度、ジョブローテーションといった人事制度を整備して活用することで、新しい職務に挑戦する機会を提供できます。従業員が希望する仕事を選べる制度によって、キャリア自律を効果的に支援できるでしょう。
管理職やマネジメント層に対する理解の促進
管理職やマネジメント層がキャリア自律について理解していないと、従業員のキャリア自律を促すことは難しいといえます。そこで、管理職を対象とした研修や、企業全体での情報共有といった施策を実施し、理解を促進させると効果的です。
社内のポストやポジションの明確化
キャリア自律を促すには、将来のキャリアをイメージしてもらうことが大切です。それには、社内のポストやポジションを明確にするとよいでしょう。一部の従業員だけでは効果が薄いので、組織全体で取り組めるように意識してください。
メンター制度を導入する
メンター制度とは、新人や若手に対して先輩をメンターに据える制度です。メンター制度があれば、新人や若手が自身のキャリアについて悩んでいても、先輩に相談できます。また、メンターを通じて自身の適性を見きわめることも可能です。
まとめ
キャリア自律は企業と従業員双方にメリットをもたらし、生産性とエンゲージメントを向上させます。個々のニーズに寄り添った支援により、企業の成長と競争力強化につながります。
人材の育成やキャリア自律の実施なら、リシテア/人財マッチングへご相談ください。リシテアのシステムは社内異動制度の運用を効率化し、社内の人財について適材適所の活用を実現します。既存の人事システムとの連携も可能となっており、優秀な人材の流出防止、新たな人材の獲得にも役立ちます。お問い合わせは下記より承ります。
関連ソリューション
リシテア/人財マッチング
社内公募・FAを効率化し、社内人材の流動化を促進、組織の活性化を支援するサービスです。