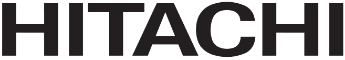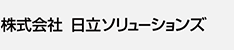人事戦略
社内公募制度のメリット・デメリット 導入の手順やポイントも紹介

「人事総合ソリューション リシテア」より人事関連のお役立ち情報のご紹介です。
社内公募制度を導入するためには、基本を理解しておく必要があります。ここでは、社内公募制度の基本を解説します。
社内公募制度は多くの企業に注目され、導入するケースも見られるようになりました。社内公募は、社内の人的リソースを最適に活用できる手段であり、従業員のモチベーション向上にも役立つ制度です。
この記事では、社内公募制度を基本から解説し、導入の手順などもまとめています。社内公募制度の導入に向けて、ぜひ参考にしてください。
社内公募制度の基本
社内公募制度とは
社内公募制度は、人材を補充したい部署が、社内からの異動希望者を募るために社内募集する制度です。人事部が制度の設定や運営を行い、募集に対して従業員が自由に応募します。制度の特徴は、従業員自身が異動希望を表明できることです。似た制度が2つあるため、次項で違いを解説します。
自己申告制度と社内公募制度の違い
自己申告制度は、従業員自身が業務経験やスキル、異動希望などを検討し、定められた申告内容を基に人事部に申告する制度です。社内公募のように、人事異動の希望を表明できるわけではありません。また、公募に対して応募する仕組みでもないのが大きな違いです。自己申告は、申告した内容が人事異動の際の参考情報となります。
社内FA制度と社内公募制度の違い
社内FA制度の「FA」は、フリーエージェントのことです。プロスポーツのように、定められた条件を満たせばFA権が付与される仕組みです。FA権を得た従業員は、異動したい部署を人事部に申告できます。社内公募制度との違いはFA権であり、FA権を有する従業員は、人事異動を希望する場合に公募を待つ必要はありません。
なぜ社内公募制度が注目されているのか
社内公募制度が注目されている大きな理由は、従業員のモチベーションが上がるからです。従業員は、自分の意思で新しい部署へ異動できるチャンスがあれば、モチベーションアップにつながります。従業員はやりがいを感じ、達成感も得られるでしょう。
また、優秀な人材の確保や人材の定着も注目されている理由です。社内公募制度は、従業員がキャリアを広げる環境づくりに役立ちます。キャリア形成のチャンスがある企業ほど、優秀な人材が定着しやすくなります。
社内公募制度を導入するメリット
多くの企業が社内公募制度の導入を検討するのは、メリットが多いからです。ここでは、代表的なメリットを3つ紹介します。
人材の定着につながる
先に触れたとおり、社内公募制度は従業員がキャリアの可能性を広げられるため、人材の定着につながります。キャリアチェンジができないことは、離職につながる原因の1つです。社内公募制度によってキャリアの選択肢が広がれば、人材は定着しやすくなるでしょう。
従業員が仕事に対して意欲的になる
適材適所の人員配置に貢献することも社内公募制度のメリットです。従業員は、自分に適した仕事に対して意欲的になり、適していなければ仕事への意欲が低下する可能性があります。
社内公募制度によって自分が望む部署に異動できれば、自分の適性に合う仕事を任せてもらえる可能性が高いでしょう。モチベーションも高い状態で維持できるため、生産性の向上も期待できます。
採用コストを削減が可能になる
採用コストを削減できることも大きなメリットです。部署は異なっても同じ会社の人間なので、理念やカルチャーは同じです。異動しても「社風に馴染まない」という可能性は低く、離職につながるリスクも限定的といえます。社内ルールなどは把握しているため、教育にあまり時間をかけず、即戦力としての活躍が期待できるでしょう。
社内公募制度を導入するデメリット
社内公募制度には、メリットがあればデメリットもあります。ここでは、デメリットを3つ紹介します。
信頼関係が崩れる可能性がある
社内公募制度に応募した事実が現在の上司に伝わると、信頼関係が崩れる恐れがあります。社内公募制度は、公募されている部署に従業員の意思で異動を立候補する制度です。社内で進めている制度に前向きな理由で異動に応募しても、今の上司がネガティブな感情を抱くケースはありえます。
人材が流出する可能性がある
部署内の人材が他部署へ流出する点も見逃せないデメリットです。社内公募制度に応募する従業員は、優秀な従業員をはじめ、ポテンシャルやモチベーションが高いなどの特徴が見られます。そのような従業員が制度を使って他部署へ異動すれば、部署内の人材流出となり戦力もダウンしかねません。
現部署の不満から応募する可能性がある
従業員が、ネガティブな理由で応募するケースは、社内公募制度のデメリットになりかねません。現在の部署の仕事を辛いと感じていたり、成果が出ていなかったりするなどの理由で応募する可能性もあります。社内公募は、前向きな制度運用が求められる制度です。ネガティブな理由での応募は、社内全体に悪影響を及ぼすかもしれません。
社内公募制度を導入する手順
社内公募制度を導入するためには、手順を知っておくとスムーズに進められます。以下で具体的な手順を解説します。
公募の資料を作成
まずは公募の資料作成から始めますが、そのためには公募内容を詳細に書き出す必要があります。詳細が明確になれば、募集要項の作成へと進みましょう。募集要項には、募集の背景や募集部署の説明、職務内容、必要なスキル、応募条件などを明記します。肝心なのは、従業員が自分に適しているかを適正に判断できる募集要項とすることです。
社内広報の実施
次に、社内広報などを通じて、社内公募制度の募集情報を全従業員に周知します。大事なのは、公募内容を公開し、全従業員が閲覧できる状態にすることです。そのためには、社内メールやポータルサイト、社内掲示板なども活用し、情報を広めなければなりません。応募方法や応募期限を明確にして、混乱を避ける配慮も大切です
応募受付を開始
従業員に周知ができたあとは、応募受付に関する明確な流れを確立しましょう。特に応募者のプライバシー保護や情報セキュリティは重要です。それらを担保しつつ、指定期間内に応募を受け付けるためには、オンラインシステムを利用するとよいでしょう。応募の管理も効率化でき、応募の秘匿性も確保しやすくなります。
書類選考や評価を実施
応募が集まり期限を迎えれば、応募書類を基に選考する段階になります。ここでのポイントは、募集要項に合致した候補者を選ぶことです。また、公平で透明性のある選考のためには、応募者の過去の成果なども選考に反映する必要があります。総合的な実力を正確に評価して選考することが、公平な選考プロセスの運用といえるでしょう。
面接選考や評価を実施
書類選考を通過した応募者に対しては、面接選考を実施しなければなりません。面接の際には、募集部署の業務遂行能力と、募集部署との適合性を重視して面接します。評価のポイントは、コミュニケーション能力や課題解決力、チームワーク力などです。面接では、応募者のキャリアデザインなども聞き出すことが求められます。
採用者を内定
面接選考で合格し、最終選考を通過した応募者には内定を正式に通知します。ポイントは、現在所属している部署の上司と、内定者本人に対して同時に通知することです。不採用となった応募者にも理由を明確に伝えるなど、内定者と同じように扱う姿勢が求められます。必要に応じてフィードバックを提供すると納得してもらいやすいでしょう。
社内公募を成功させるポイント
社内公募制度の成功は自社の成長につながります。そこで、社内公募制度を成功させるポイントを解説します。
従業員に周知
社内公募制度は、公募を全従業員に周知することが重要です。公募がある際には説明会などを開催して全従業員に周知しましょう。周知する際には、従業員から制度と募集内容の理解を得ることも重要です。周知が徹底できていないと、ネガティブに受け止められる可能性もあります。ポジティブな制度であることも、従業員から理解を得なければなりません。
応募条件を詳細に設定
応募条件をできるだけ詳しく設定することも重要なポイントです。応募条件があいまいでは、応募に意欲的な従業員がいても二の足を踏んで応募しない可能性があります。そうなれば、モチベーション向上や組織の活性化などの目的達成は難しいでしょう。必要なスキルや必要な経験、望まれる資格などを軸に応募条件を詳細に決めれば、従業員が理解しやすくなります。
異動後のサポート
社内公募制度は、人材を求めている部署に人材を配置すれば終わりではありません。異動した従業員が部署で機能しているか、部署に馴染んでいるかなどを確認します。そして、異動後のサポートも欠かさずに行いましょう。具体的には、フォローできる支援体制の構築が望まれます。また、異動前の部署でやり残した仕事にもフォローが必要です。
まとめ
社内公募制度には、人材を定着させたり、従業員のモチベーション向上につながったりするメリットがあります。また、社内の人材を活用するため、採用にかかるコストや労力も削減可能です。部署からの要請があれば、公募を全従業員に周知させて社内人事の活性化を図りましょう。
人事異動の効率化を図るのであれば、リシテア/人財マッチングの利用を検討ください。社内異動制度の運用を効率化し、複数の異動制度を管理できます。既存のシステムとも連携可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
日立ソリューションズでは、人事戦略を製品にいかしています。
人事課題に対するお悩み、人事DXについてのご相談などお気軽にお問い合わせください。
関連ソリューション
リシテア/人財マッチング
社内公募・FAを効率化し、社内人材の流動化を促進、組織の活性化を支援するサービスです。